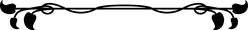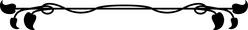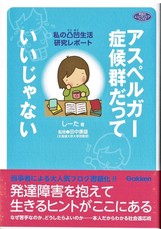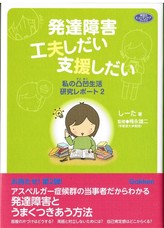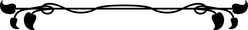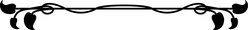Request for Lecture
講演・講師の依頼
発達障害・不登校に関する下記のご依頼を承っております。
- 発達障害に関する講演・ワークショップ
各地の発達障がい者支援センター、都道府県や教育委員会主催の教職員研修などの実績多数 - 心のケアのためのアートセラピー
- 発達障害・不登校の子どもの教育についてのコラム・著書の執筆
Books
著書
Lecture
講演
発達凸凹を活かそう!
ー「弱み」を誰にも負けない「強み」に変えるためにー
本講演は、各地の発達障がい者支援センター、保健所、教職員研修、福祉協議会、NPOなど、すでに20回に至る人気高いの講演です。発達障害の当事者・家族・支援者のすべての方に、未来への希望と可能性を感じていただける内容です。
もちろん、「発達障害って何?」という、一般の方にもわかりやすい内容となっています。
依頼される講演のほとんどが、実際に講演を聞いた方からの「この講演の内容がよかったので、うちの施設・地域の人にも聞かせたい」という形で来られます。それだけ、分かりやすく質の高い内容になっています。
次の3つのテーマに沿って話をすすめます。
1.私のやりかたは間違ってるの?
発達障害の人の支援や教育の中で、一番問題になるのが、よく事情をしらない周囲の人からの無責任なアドバイス的なものに、惑わされて、不安や迷いが生じてしまう。それこそが、うまくいかない原因だということ。
そして、大切な3つのポイントを挙げて、その3つを実践することで、「弱み」が「強み」に転じるメカニズムについて、具体例を交えてお話します。
2.目的と手段を間違えてない?
「九九を覚えられないと落ちこぼれ?」という問いから始め、具体例を挙げながら、目的は、九九を覚えることではなく、正確な計算をすること。つまり、九九は「目的」ではなく、目的達成のための「手段」の1つに過ぎないのです。
このように、発達障害支援の多くが「手段」を「目的」と勘違いして行われているために、失敗と挫折の繰り返しになっているのです。まず、「手段」を「目的」と見誤らないこと。それこそが、発達障害支援で解決すべき根本的問題なのです。
次に、発達障害の人が「できないこと」を「できる」にするというのはどういうことなのか、その根底から考え直していきます。
3.苦手解決をするための手順
発達障害の当事者である私自身の体験から、「自分にあった工夫」を見つける方法をまとめてみました。
苦手の難易度を判定や、「苦手解決サイクル」のPDCA(Plan-Do-Check-Action)について、具体例を交えてお話しします。
もちろん、「発達障害って何?」という、一般の方にもわかりやすい内容となっています。
依頼される講演のほとんどが、実際に講演を聞いた方からの「この講演の内容がよかったので、うちの施設・地域の人にも聞かせたい」という形で来られます。それだけ、分かりやすく質の高い内容になっています。
次の3つのテーマに沿って話をすすめます。
1.私のやりかたは間違ってるの?
発達障害の人の支援や教育の中で、一番問題になるのが、よく事情をしらない周囲の人からの無責任なアドバイス的なものに、惑わされて、不安や迷いが生じてしまう。それこそが、うまくいかない原因だということ。
そして、大切な3つのポイントを挙げて、その3つを実践することで、「弱み」が「強み」に転じるメカニズムについて、具体例を交えてお話します。
2.目的と手段を間違えてない?
「九九を覚えられないと落ちこぼれ?」という問いから始め、具体例を挙げながら、目的は、九九を覚えることではなく、正確な計算をすること。つまり、九九は「目的」ではなく、目的達成のための「手段」の1つに過ぎないのです。
このように、発達障害支援の多くが「手段」を「目的」と勘違いして行われているために、失敗と挫折の繰り返しになっているのです。まず、「手段」を「目的」と見誤らないこと。それこそが、発達障害支援で解決すべき根本的問題なのです。
次に、発達障害の人が「できないこと」を「できる」にするというのはどういうことなのか、その根底から考え直していきます。
3.苦手解決をするための手順
発達障害の当事者である私自身の体験から、「自分にあった工夫」を見つける方法をまとめてみました。
苦手の難易度を判定や、「苦手解決サイクル」のPDCA(Plan-Do-Check-Action)について、具体例を交えてお話しします。
参加者の声
- 苦手なことばかりに目を向けがちで、落ち込んでばかりでしたが、お話を聞いて、弱みも強みに変えられるんだと、前向きな気持ちになりました。
- 今まで自分の苦手なことを何とかしようとばかり考えていました。今日のお話を聞いて、苦手なことは一度置いておいて、得意なことを伸ばすことが大切なのだと分かりました。困難な事の判定なども、今まで、あまり深く考えたことがありませんので、しっかりと自己分析したいと思います。
- 今まで、周りの人からのつっこみに迷ったり不安になっているままで、やっていたけど、自分のやり方を考えて、自信をもってやらないと、もともとできないことは、できないのは当たりまえ、との言葉に、ハッとしました。自分でしっかり考えて、やってみようという、ヤル気を今回の講座を受けて、いただけたような気がします。
- 最終目的に目を向けること、難易度の見極めなどを教えていただき、今後の娘のこと(弱点)を見守る糸口が見えました。
- 苦手な部分を無理させず「避ける」にはちょっと驚きでしたが、他の部分でおぎなっていくのも手ですね。
- どのお話もとてもわかりやすく勉強になりました。これからの支援や工夫でとても参考になるものばかりなので助かります。
- 苦手克服を具体例を挙げて説明されたので、非常に役に立った。
- 1つのテーマにしぼり、とてもわかりやすくきっちりと伝えてくださったこと。本人が自己認知を深め、自己支援をできていくようになるのに、TEACCHの再構造化をうまくとりいれた内容がとてもよかったです。
講演実績
(2012年~)
(2012年~)
|
一般講演
|
教職員研修
|
不登校・発達障害の子どもが伸びる学び方
ー親がすべきたった1つのことー
(現在、準備中です。)
Workshop
ワークショップ
発達障害のコミュニケーションに本当に必要なコト
ー最大の原因は「前提」の違いにあった!ー
発達障害の一番難しい問題が「コミュニケーション能力」だと言われています。
「どんなに努力をしても、うまくコミュニケーションが取れるようにならない…。」
当事者本人・家族・支援者の共通の悩みではないでしょうか?
言い換えれば、発達障害の問題の多くは、コミュニケーションがうまく取れれば、解消するものが多いのです。
そのことは、当事者・家族・支援者も、理解はしていて、努力をしているにもかかわらず、あまり効果がないことが多いのは、なぜなのでしょうか?
その理由は、ただ1つ。
発達障害の当事者とそれ以外の人の間には、全てのベースとなる「前提」の違いがある。
それだけなのです。
たったそれだけのことに気づけば、全てが大きく変わります。
だからこそ、発達障害の人とそれ以外の人のコミュニケーションでは、前提の違いを配慮しながら伝えるチカラが必要なのです。そして、発達障害の人が身につけるべきチカラは、「前提の違い」に気づいて、不足している情報を訊きだすチカラが必要なのです。
簡単なグループワークを通して、「前提」の違いとはどういうものなのかを体感していただきます。
そして、発達障害の人と周囲の人のコミュニケーションの質を上げるために、どのような工夫が必要なのかについて、お話をしていきます。
「どんなに努力をしても、うまくコミュニケーションが取れるようにならない…。」
当事者本人・家族・支援者の共通の悩みではないでしょうか?
言い換えれば、発達障害の問題の多くは、コミュニケーションがうまく取れれば、解消するものが多いのです。
そのことは、当事者・家族・支援者も、理解はしていて、努力をしているにもかかわらず、あまり効果がないことが多いのは、なぜなのでしょうか?
その理由は、ただ1つ。
発達障害の当事者とそれ以外の人の間には、全てのベースとなる「前提」の違いがある。
それだけなのです。
たったそれだけのことに気づけば、全てが大きく変わります。
だからこそ、発達障害の人とそれ以外の人のコミュニケーションでは、前提の違いを配慮しながら伝えるチカラが必要なのです。そして、発達障害の人が身につけるべきチカラは、「前提の違い」に気づいて、不足している情報を訊きだすチカラが必要なのです。
簡単なグループワークを通して、「前提」の違いとはどういうものなのかを体感していただきます。
そして、発達障害の人と周囲の人のコミュニケーションの質を上げるために、どのような工夫が必要なのかについて、お話をしていきます。
参加者の声
- 伝えるのも訊くのも難しいと思っていたけど、どういうふうに難しいかが、ワークショップで具体的に身をもって体験したので、よかった。発達障害以外の人にも、たくさん聞いてほしいと思う内容でした!
- しーたさんの本を読んでいたので、「前提の違い」があるというのは知っていましたが、実際にワークをしてみると、それぞれの前提が違うことが分かり、おもしろかったです。今後、少しずつ、前提の違いを意識しながら、コミュニケーションをとってみようと思います。
- 最後のワークで、前提のちがいに気づけてないことが、実感できた。訊く方で自信がなかったけど、自分なりによくきけたと思う。少人数で最初緊張したが、楽しめました。機会があれば、また参加したいです。ありがとうございました。
- 支援者です。当事者でもある、しーたさんの経験をもとに考え出された支援について、当事者の考え方等を学べて、大変勉強になりました。また、参加者の中に当事者の方もいらっしゃり、一緒にワークをすることで、一人一人のちがいをさらに気づくことができました。
- 当事者支援だけでなく、自分自身の生活全般にとても役立つイベントでした。普段から、会話の中で感じる「あれ?」という違和感がキーポイントなのですね。説明力や質問力を練習して伸ばしていきたいです。
- 内容がすごく具体的で、テーマにピッタリ沿っていた。例題もイメージしやすかった。普段と違い、講師始め、皆が当事者だから安心できた。「前提の違い」と「同じ事を皆がイメージしてると思うのは間違い」というのはインパクトがあった。何より「ここでは不安に思わなくていい」という空気感がいい。視覚・聴覚・触覚、いろんな過敏があると再認識した。
- 「前提のちがい」という言葉が、すごくわかりました。すっと心に入りました。
今まで、相手が考えていることを何故?とギモンに思いながら、話を聞いていましたが、前提が違う、それは、育ってきた環境、体験していることが違うから発生しうることと理解できました。発達の方の「訊く力」データベースを作り上げる環境も、力はあるけど、過去の失敗の体験から、その力が発揮できないことを知り、今後の関わりに活かしたいと思います。「質問力」も、どう伝えてあげるか、学べました。
講演実績
2015-2016年
東京・大阪、名古屋にて自主講演開催
学研「実践障害児教育 11月号」に掲載
2018年
豊中市立西丘小学校(小5・6年生対象)
東京・大阪、名古屋にて自主講演開催
学研「実践障害児教育 11月号」に掲載
2018年
豊中市立西丘小学校(小5・6年生対象)
|
Copyright© でこぼこ楽伸会 2017- All rights reserved.
|